
Tractatusの構造を示す図解。 5764>
本文には7つの主要な命題がある。 5087>
- The world is everything that is the case.
- What is the case (a fact) is the existence of states of affairs.
- A logical picture of facts is a thought.
- A thought is a proposition with a sense.
- A proposition is a true-function of elementary propositions.
- The world is everything is a case.
- What is the case (a fact) is the existence of states of affairs. (初等命題はそれ自体の真理関数である。)
- 命題の一般形式は真理関数の一般形式であり、それは次の通りである。 {displaystyle}
. これは命題の一般形である。
- Whereof one cannot speak, thereof one must be silent.
命題1編集
第1章は非常に短い。
- 1 世界とはすべてのことを言うのだ。1 世界は事実の総体であって、事物の総体ではない
- 1.11 世界は事実によって、また事実がすべてであることによって決定される
- 1.12 事実の総体は、事実であるもの、また事実でないものを決定するからである
- 1.12.13 論理空間における事実が世界である
- 1.2 世界は事実に分割される
- 1.21 それぞれの項目は、他のすべてが同じままであっても、事実であったり事実でなかったりすることができる。
これは2の冒頭とともに、ウィトゲンシュタインの形而上学的見解の関連部分であり、彼が言語の絵理論を支えるために使用するものと考えられる。
提案2および3編集
これらの部分は、我々が知覚する感覚的に変化する世界は物質からではなく、事実で成り立っているというウィトゲンシュタインの見解に関するものである。 命題2は、対象、形態、実体についての議論から始まる。
- 2 何が事実なのか–事態の状態の存在である。
- 2.01 事態(の状態)は対象(物)の組合せである。
この認識論的概念は、形而上学的物質としての物体あるいは事物についての議論によってさらに明らかにされる
- 2.0141 原子的事実におけるその発生の可能性がオブジェクトの形態である
- 2.02 オブジェクトは単純である
- …
- 2.021 オブジェクトは世界の実質を構成している。 だからこそ、それらは複合的であることができないのだ。
2.021における彼の「複合」という言葉の使用は、プラトン的意味での、形と物質の結合を意味すると考えられる。
静的で不変な形とその物質との同一性の概念は、プラトンおよびアリストテレス以来、西洋哲学の大多数の者が同意したこととして前提として持つようになった形而上学的見解の代表的なものである。 “形や物質と呼ばれるものは、生成されたものではない。” (Z.8 1033b13)反対意見は、不変の形は存在しないか、少なくともそのようなものがあるとすれば、そこには常に変化し続ける相対的な物質が含まれているとするものである。 この見解はヘラクレイトスのようなギリシア人が持っていたが、それ以来、西洋の伝統の片隅にのみ存在していた。 現在では、「東洋」の形而上学的見解においてのみ一般的に知られている。そこでは、物質の主要な概念は気、あるいはそれに類似したものであり、いかなる形をも貫いて、それを超えて存続するものである。 5087>
- 2.024 実体とは何であるかとは無関係に存続するものである
- 2.025 形と内容である
- 2.026 世界が不変の形を持つためには、対象が存在しなければならない
- 2.027 対象、不変のもの、実質的なものは、一体である
- 2.028
- 2.0271 物体は不変で実質的なものであり、その構成は変化し不安定なものである
ウィトゲンシュタインはアリストテレスをほとんど無視していたが(レイ・モンクの伝記では彼は全くアリストテレスを読まなかったらしい)、一次物質に関する普遍/特殊問題では反プラトン主義的見解を共有したと思われる。 彼は『青本』の中で普遍性を明確に攻撃している。「一般概念はその特定のインスタンスに共通の性質であるという考え方は、言語の構造に関する他の原始的で単純すぎる考え方に通じるものがある。 例えば、アルコールがビールやワインに含まれるように、美はすべての美しいものの成分であり、したがって、美しいものによって汚されていない純粋な美を持つことができるという考え方に匹敵する」
そしてアリストテレスも同意している。 “普遍は本質がそうであるように物質であることはできない……” (Z.13 1038b17)と、師プラトンの普遍形式の概念から一線を引いて離れ始めている。
本質の概念は、単独では可能性であり、物質との結合が現実性である。 “第一に、あるものの実体はそのものに特有であり、他のいかなるものにも属さない”(Z.13 1038b10)、すなわち普遍的ではなく、これが本質であることがわかる。 この、今ひとつに折り畳まれた形/実体/本質が可能性として提示されるという概念は、ウィトゲンシュタインも持っていたらしい:
- 2.033 形とは構造の可能性
- 2.034 ある事実の構造は状態の構造から成る
- 2.04 現存する諸状態の総体が世界である.
- 2.063 現実の総体が世界である.
ここでウィトゲンシュタインの形而上学の見解の関連点と考えられるものが終わり、彼は2・1で当該見解を用いて彼の言語の絵理論を支持し始めるのである。 トラクタートス』の実体概念は、カントの時間的概念の様相類似である。 カントにとって実体とは「持続する」ものであるのに対し、『トクトゥス』の実体概念は、カントの時間的概念の様相的類似である。 アリストテレス的な実体概念は、イマニュエル・カントを経由して、あるいはバートランド・ラッセルを経由して、あるいはウィトゲンシュタインが直感的にその概念に到達したにせよ、それを見ずにはいられない」
2、3およびその補助命題のさらなるテーゼは、ウィトゲンシュタインの言語絵画論である。 これは次のように要約される:
- 世界は相互に結びついた原子的事実の全体からなり、命題は世界の「絵」を作る。
- ある絵をある事実を表すためには、何らかの形でその事実と同じ論理構造を有していなければならない。 絵は現実の基準である。 このように、言語表現は幾何学的投影の一形態と見ることができ、言語は変化する投影の形態であるが、表現の論理構造は不変の幾何学的関係である。
- 構造において何が共通かを言語で言うことはできず、むしろそれは示されなければならない。なぜなら我々が使ういかなる言語もこの関係に依存するので、言語をもって我々の言語から踏み出すわけにはいかないからである。
命題4・Nから5・NEdit
4は、哲学の本質と、言えることと示すことしかできないことの区別に関するウィトゲンシュタインの最も明確な発言を含んでいるので重要である。 たとえば、彼はここで初めて、物質的命題と文法的命題を区別し、次のように指摘しています。
4.003 哲学的著作に見られる命題や質問のほとんどは偽ではなく、無意味である。 したがって、この種の質問に対しては、いかなる答えも与えることができず、ただ無意味であることを指摘することしかできない。 哲学者の命題や疑問のほとんどは、私たちの言語の論理を理解できていないことから生じています。 (それらは、善は美よりも同一性が高いか低いかという問いと同じクラスに属します)。 そして、最も深い問題が実際にはまったく問題ではないことは驚くべきことではない。
哲学的論文は、何も適切に言うことができないところで何かを言おうとしているのである。 これは、哲学は自然科学に類似した方法で追求されるべきであり、哲学者は真の理論を構築することを目的としているという考えに基づいている。 このような哲学の感覚は、ウィトゲンシュタインの哲学の概念とは一致しない。
4.1 命題は状態の存在と非存在を表す
4.11 真の命題の全体は自然科学の全体(あるいは自然科学の全コーパス)である
4.111 哲学は自然科学の一つではない
4.111 哲学は自然科学を代表する一つではない
4.111 哲学は自然科学の一つである4.2 真の命題の全体は、自然科学の全体である。 (哲学という言葉は、その位置が自然科学の上または下にあるものを意味しなければならず、それらの横にあるものではない)
4.112 哲学は、思考の論理的解明を目指すものである。 哲学は教義の体系ではなく、活動である。 哲学的著作は、本質的に解明からなる。 哲学は「哲学的命題」に帰結するのではなく、命題を解明することに帰結するのである。 哲学がなければ思考はいわば曇り、不明瞭である。哲学の仕事はそれらを明確にし、鋭い境界を与えることである
…
4.113 哲学は自然科学の多くの議論のある領域に限界を設ける
4.114 考えることができるものに限界を設け、そうすることで考えることができないものに限界を設けなければならない。 5087>
ウィトゲンシュタインは、現在一階文言論理の標準的な意味論分析を構成する真理表(4.31)と真理条件(4.431)の発明あるいは少なくとも普及で評価される。 ウィトゲンシュタインにとって、このような方法の哲学的意義は、論理的推論が規則によって正当化されるという考え方の混乱を緩和することであった。 ある論証形式が妥当であれば、前提の連立は結論と論理的に等価になり、これは真理値表で明確に見ることができる;表示されるのである。 同語反復の概念は、このように厳密に演繹的であるウィトゲンシュタインの論理的帰結のトラクトの説明の中心である。
5.13 ある命題の真理が他の命題の真理から続くとき、我々は命題の構造からこれを見ることができる
5.1.131 ある命題の真理が他の命題の真理から導かれる場合、このことは命題の形式が互いに立つ関係において表現されることがわかる。また、これらの関係を一つの命題の中で互いに結合してそれらの間に設定する必要はない。それどころか、この関係は内部的であり、その存在は命題の存在の直接的結果であるのである。
…
5.132 pがqから導かれるならば、qからpへの推論を行い、qからpを演繹することができるが、この推論の性質は二つの命題からのみ収集することができる。 この2つの命題自体が、推論を正当化する唯一の可能性である。 フレーゲやラッセルの著作のように推論を正当化するとされる「推論の法則」は意味を持たず、余計なものである。
命題6・NEdit
命題6の冒頭でウィトゲンシュタインは全ての文の基本形を提唱している。 彼は{}という記法を用いている。

, ここで
- p ¯ {displaystyle {bar {p}}} は、以下の通りです。
はすべての原子命題、
- ξ¯ {displaystyle {bar {xi }} を表します。}
stands for any subset of proposition, and
- N ( ξ ¯ ) {displaystyle N({ Thenbar {xi }})
stands for negation of all propositions making up ξ ¯ {displaystyle {bar {}xi }} を構成するすべての命題の否定を表す。
.
命題6は、任意の論理文は原子命題の全体に対する一連のNOR操作から導き出すことができるとするものである。 ウィトゲンシュタインはヘンリー・M・シェファーの論理定理から、命題計算の文脈でこのステートメントを導き出したのである。 ウィトゲンシュタインのN-演算子は、シェファーのストロークのより広い無限のアナログであり、命題の集合に適用すると、その集合のすべてのメンバーの否定と等価である命題を生成する。 ウィトゲンシュタインは、この演算子が同一性を伴う述語論理の全体に対処できることを示し、5.52で量詞を定義し、5.53-5.532で同一性がどのように扱われるかを示しています。
6.の子会社には論理に関するより哲学的な考察が含まれており、知識、思考、アプリオリと超越の概念に接続されています。 最後の箇所は、論理学と数学は同語反復のみを表し、超越的である、すなわち形而上学的主体の世界の外にあることを主張する。 5087>
『論文集』は、命題6.4-6.54から、その焦点を主として論理的考察から、より伝統的に哲学的な焦点(神、倫理、メタ倫理、死、意志)、そして、これらと同様にあまり伝統的ではない神秘的なものと見なすことができるものへと移行している。 Tractatus』で提示される言語哲学は、言語の限界とは何かを明らかにしようとするもので、感覚的に何が言えて、何が言えないかを明確にしようとするものです。 ウィトゲンシュタインにとって、感覚的に言えるものの中には、自然科学の命題があり、非感覚的、あるいは言えないものの中には、例えば、倫理学や形而上学など、伝統的に哲学に関連する主題があります。 不思議なことに、この点に関して、『論考』の最後から二番目の命題である6.54は、『論考』の命題を理解すれば、それらが無意味であることを認識し、それらを捨てなければならないと述べているのである。 この命題6.54は、解釈上、難しい問題を提起している。 もし、いわゆる「意味の絵理論」が正しく、論理的形式を表現することが不可能であるならば、この理論は、意味が存在するために言語と世界がどのようにあるべきかということについて何かを言おうとすることによって、自己破壊していることになるのである。 つまり、意味の「絵理論」自体が、意味がありうるために文が現実と共有しなければならない論理形式について何かを語ることを要求しているのである。 このことは、意味の「絵空事」理論が排除していることをまさに行うことを要求しているのである。 そうすると、『トラクタート』が支持する形而上学と言語哲学は、あるパラドックスを生んでいるように思われる。 しかし、この自己適用によって『Tractatus』の命題が(Tractarianの意味で)ナンセンスになるためには、『Tractatus』は真でなければならない。
このパラドックスを解くために、主に次の三つの弁証法的アプローチがある 伝統主義、すなわち「不可触知」観、2)断固たる「新Wittgenstein」、すなわち「すべてナンセンス」観、3)「まったく真実でない」という観方。 このパラドックスを解決するための伝統主義的アプローチは、ウィトゲンシュタインは、哲学的な言明はできないが、それでも、言うことと示すことの区別に訴えることによって、これらの真理は示すことによって伝えることができると認めたとするものである。 毅然とした読み方では、『トラクタート』の命題のいくつかは自己適用が差し控えられ、それ自体がナンセンスなのではなく、『トラクタート』のナンセンスな性質を指摘することになる。 この見解は、『トラクタート』の序文と命題からなるいわゆる「枠」にしばしば訴えられる。 真偽不明説は、ウィトゲンシュタインが『講義録』の命題を、真であると同時に無意味であるという曖昧なものであるとしたものである。 この命題は、『論考』に付随する哲学の自己適用によって真になる(あるいは感覚的になる)ことはできないが、『論考』の哲学そのものがそうさせることができるに過ぎないのである。 このことが、ウィトゲンシュタインに、哲学の問題を特別に解決したものとして『ト ラクタトゥス』の哲学を受け入れざるを得なくさせたのであろう。 問題を解決できるのは、『論考』の哲学だけなのである。 5087>
本文の最後にウィトゲンシュタインはアルトゥール・ショーペンハウアーのアナロジーを用いて、本を登った後に捨てなければならない梯子に例えている。 この命題は、”Whereof one cannot speak, thereof one must be silent. “という命題でこの本を終えている。 (Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.”)
The picture theoryEdit
『Tractatus』で示された著名な見解に、言語の絵理論(picture theory of language)と呼ばれることがあります。 p44 世界にあるものを表すのに命題である必要はないが、ウィトゲンシュタインは命題が表象としてどのように機能するかに大きく関心を寄せていた。 もし誰かが「庭に木がある」という命題を考えたとしたら、その命題は「庭に木がある」場合にのみ、世界を正確に描写する。:p53 ウィトゲンシュタインが言語と比較して特に照明的だと考える絵の一側面は、その状況が実際に得られるかどうかを知らなければ、それが描いている状況を絵で直接見ることができるという事実である。 このことは、ウィトゲンシュタインが、(ラッセルが長年苦心した問題である)偽の命題が意味を持ちうることを説明することを可能にする。ちょうど、絵から、それが実際に得られるかどうかを知ることなく、それが描いている状況を直接見ることができるように、同様に、我々が命題を理解するとき、それが実際に正しいかどうかを知らず、その真実条件あるいはその意味を把握し、すなわち、それが真ならば世界がどうあるべきかを知っている(TLP 4.5087>
ウィトゲンシュタインは、パリの交通裁判所で自動車事故が再現される様子からこの理論の着想を得たとされている:p35 おもちゃの自動車は本物の自動車の、おもちゃのトラックは本物のトラックの、人形は人間の表象である。 自動車事故で何が起こったかを裁判官に伝えるために、法廷にいる誰かが、おもちゃの車を本物の車が置かれていたような位置に置き、本物の車の動きと同じように動かすことがあるのです。 このように、絵の要素(おもちゃの車)は互いに空間的な関係にあり、この関係自体が自動車事故の実際の車の間の空間的な関係を描いている。 これは、絵の中の絵の要素の論理的に可能なすべての配置が、それらが描いているものを現実に配置する可能性に対応していることを意味する。 したがって、もし車Aの模型が車Bの模型の左側に立っていれば、それは世界の車が互いに同じように相対して立っていることを描いていることになる。 ウィトゲンシュタインは、この絵画的関係こそが、命題が世界とどのような関係にあるかを理解する鍵であると考えたのである。 言語は絵とは異なり、直接的な絵画的表現様式を持たないが(例えば、色や形を表現するために色や形を使わない)、それでもウィトゲンシュタインは、命題は、それが表現する現実と論理的形態を共有することによって、世界の論理的絵になると考えた(TLP 2.18-2.2 )。 そしてそのことが、命題の意味が説明されなくても我々が命題を理解できる理由を説明していると考えた(TLP 4.02)。我々は、その描写方法を知っているだけでそれが描写している状況を絵に見るように、命題にそれが表しているものを直接見ることができる:命題はその意味を示す(TLP 4.022)<5087><32>しかし、ウィトゲンシュタインは、絵がそれ自体の論理形態を表せない、現実と何を共有しているのかは言えないがそれを示すことしかできない、と主張した(TLP 4.12-4.121). もし表現が論理空間における要素の配置を描くことにあるとすれば、論理空間自体が何かの配置ではないので、描くことはできない。むしろ論理形式はオブジェクトの配置の特徴であり、したがってそれは(論理構文によって規定されるのと同じ組み合わせの可能性を含む)文における関連記号の類似の配置によって言語で適切に表現(つまり描く)ことができ、したがって論理形式は異なる文の間の論理関係を提示することによってのみ示されうるのである。
ウィトゲンシュタインの絵画化としての表現概念はまた、先験的に知ることのできる命題はない-先験的真理は存在しない(TLP 3.05)、および論理的必然性だけがある(TLP 6.37)という二つの顕著な主張を導き出すことを可能にするものであった。 すべての命題は絵であることによって、現実に起こっていることとは無関係に意味を持つので、命題だけからそれが正しいかどうかを見ることはできず(もし先験的に知ることができるならそうなる)、それが正しいことを知るためには現実と比較しなければならない(TLP 4.031 “In the proposition a state of affairs is asite as well for the experiment.” )。 また、同様の理由で、ウィトゲンシュタインが意味を欠くとする同語反復の限定的な場合を除き、いかなる命題も必ずしも真ではない(TLP 4.461)。 ある命題が論理空間における絵であることを理由にある状態を描くとすれば、非論理的あるいは形而上学的な「必要真理」は、どんな可能な物の配置によっても満たされる状態(どんな可能な状態に対しても真なので)となるが、これは、必要命題となるものが何もそうであると描かず、世界が実際にどうであっても真となることを意味している。 しかし、もしそうであれば、その命題は世界について何も言うことができないし、世界におけるいかなる事実も記述することができない – それは同語反復のように、いかなる特定の状態にも相関しない(TLP 6.37)
論理的原子論 編集
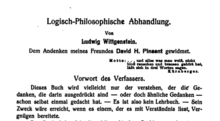
ラッセルの記述論は、明確な記述を含む文を、その記述を満たす対象の存在を前提にすることなく論理的に分析する方法である。 この理論によれば、「私の左側に男がいる」というような文は、次のように分析されるはずである。 「xが男でxが私の左にいるようなxがあり、任意のyについて、yが男でyが私の左にいる場合、yはxと同一である」。 この文が真であれば、xは私の左隣の男を指す」
ラッセルは自分の理論における名前(xなど)は、知己のおかげで直接知ることができるものを指すべきだと考えたのに対し、ウィトゲンシュタインは論理分析に何らかの認識論的制約があるとは考えなかった:単純対象は、それ以上論理的に分析できない初等命題に含まれていれば、何でもいいのである。p63
対象というのは、世界の物理的対象ではなく、組み合わせることはできても分割することはできない、論理分析の絶対的基盤を意味した(TLP 2.02-2.0201 )。 ウィトゲンシュタインの論理解剖学的形而上学体系によれば、対象はそれぞれ「性質」を持っており、それは他の対象と結合する能力を持つということである。 結合されたとき、物体は “状態 “を形成する。 そうして得られた状態が “事実 “である。 事実は、世界の全体を構成している。 事実も状態と同様に、論理的に互いに独立している。 つまり、ある状態(または事実)が存在しても、別の状態(または事実)が存在するかしないかを推論することはできないのである。 5087>
ある事実は、マディソンがウィスコンシン州にいるという獲得状態として考えられるかもしれないし、マディソンがユタ州にいるという可能な(しかし獲得できない)状態として考えられるかもしれない。 これらの状態は、ある種の物体の配置によって成り立っている(TLP 2.023)。 しかし、ウィトゲンシュタインは対象が何であるかは明示していない。 マディソン、ウィスコンシン、ユタが原子的対象であるはずはなく、それ自体が多数の事実によって構成されている。 しかし、私たちの言語は、そのような相関のために十分に(つまり、完全に)分析されていないので、対象が何であるかを言うことはできない。 ウィトゲンシュタインは、哲学者の仕事は分析を通じて言語の構造を発見することだと考えた:p38
アンソニー・ケニーは、ウィトゲンシュタインの論理的原子論を理解するために、少し修正したチェスのゲームという有用なアナロジーを提供している:p60-61 状態のオブジェクトと同様に、チェスの駒は単独ではゲームを構成しない-駒(オブジェクト)自体と共に、それらの配置が状態を決定するのである。
ケニーのチェスのアナロジーを通して、ウィトゲンシュタインの論理的原子論と彼の表象の絵理論との関係を見ることができる。:p61 このアナロジーのために、チェスの駒はオブジェクトであり、それらとその位置は事態の状態、したがって事実を構成し、事実の全体はチェスの特定のゲーム全体である。
我々は、ウィトゲンシュタインの言う命題が世界を表わすのと同じ方法でこのようなチェスのゲームを伝えることが出来る。 私たちは、白のルークが一般に王のルーク1とラベル付けされたマスにあることを伝えるために「WR/KR1」と言うかもしれません。 あるいは、もっと徹底して、すべての駒の位置についてこのような報告をするかもしれません。
私たちの報告の論理的形式は、意味を持つためには、チェスの駒とボード上のその配置の論理的形式と同じでなければなりません。 チェス・ゲームに関する我々のコミュニケーションは、ゲームそのものと同じように多くの構成要素とその配置の可能性を持っていなければならない。 ケニーは、このような論理形式はチェスゲームと厳密に類似している必要はないと指摘する。 論理的な形は、ボールのバウンドによって持つことができる(例えば、20回バウンドすれば、白ルークが王のルーク1のマスにあることが伝わるかもしれない)。 ボールは何度でも弾むことができるので、ボールの弾みは「論理的多重性」を持ち、ゲームの論理形式を共有することができる。
言うことと示すことの区別Edit
『Tractatus』の従来の読み方によれば、論理と言語に関するウィトゲンシュタインの見解から、言語と現実のある特徴は感覚的言語では表現できず、ある表現の形式によって「示される」だけだと考えるようになった。 したがって、たとえば、絵画理論によれば、ある命題が思考されたり表現されたりするとき、その命題は、その現実とある特徴を共通に持つことによって、(真にも偽にも)現実を表していることになる。 しかし、その特徴そのものは、ウィトゲンシュタインが「何も言えない」と主張したもので、絵が描くものとの関係を記述することはできず、事実を記述する命題を介して示すだけだからだ(TLP4.121)。 したがって、言語と現実の間に対応関係があるとは言えないが、対応関係自体は示すことができる(p56)。p47
しかし、最近の『トラクタート』の「毅然とした」解釈(下記参照)では、「示す」ことに関する発言は、実際には、言語や現実の何らかの不可解な特徴の存在を示唆するウィトゲンシュタインの試みではなく、むしろ、コーラ・ダイヤモンドやジェームズ・コナンが論じたように、この区別は論理と説明的談話の間に鋭いコントラストを描くことを意味していたのだ。 彼らの読みでは、ウィトゲンシュタインは確かに、私たちが言語の論理を考察するときに、あることが示されることを意味します。しかし、示されるのは、私たちが何らかの理由でそれを考えることができる(したがって、ウィトゲンシュタインが示そうとすることを理解できる)けれど、何らかの理由でそれを言うことができないかのように、何かがそうであるということではないでしょうか。 ダイヤモンドとコナンが説明しているように、
話すことと考えることは、論理的な側面を持たない実践的な習得が必要な活動とは異なりますし、その活動に特有の内容の習得が必要な物理学のような実践的な習得とは異なります。 ウィトゲンシュタインの考えでは、言語の習得は、ある種の内容についての暗黙の習得にさえ依存しない。 活動そのものの論理的な表現が、私たちが何かを意識することなく、より明確に見えてくるのです。 哲学的解明の活動について語るとき、文法は、その活動の結果について述べる際に、 「that」句と「what」構文の使用を私たちに強いるかもしれません。 しかし、最後の「梯子をはずす」行為には、『トラクタート』を読み進めていく中で、「何」であるかという文法が私たちを広く惑わせてきたことを認識することが含まれると言えるでしょう。 5087>
同様に、マイケル・クレーマーは、ウィトゲンシュタインの言うことと示すことの区別を、ギルバート・ライルの「それを知ること」と「どのように知ること」の有名な区別と比較できることを示唆しました。 ライルによれば、(自転車に乗るような)実用的な知識や技能が命題的な知識に還元されないのと同様に、ウィトゲンシュタインも、我々の言語の論理の習得は、いかなる命題的な「それを知っている」ことを伴わない独特の実用技能であり、むしろ感覚的に文を操作してその内部論理関係を把握する我々の能力に反映されると考えていました<5087>。


